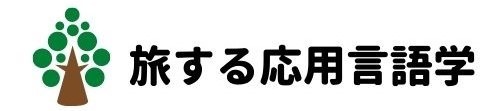音声学と音韻論の違い
音声学(phonetics)と音韻論(phonology)は、どちらも「音声」を扱うということで似ています。二つは重複することも多いのですが、以下のような違いがあります。
- 音声学:言語音の諸特徴を記述する
- 音韻論:意味の弁別に関与する最小単位である音素の特定やその分布の研究を行う(庵 2001, p. 4)
これだけではわかりづらいので、具体例を出して考えてみます。
「音素とは何か」の記事でも書きましたが、日本語では音素の/N/があります。日本語の「ん」に当たる音です。
ただ、この「ん」の音は、実は後に続く音によって発音が変わると言われています。
- さんま[samma]
- さんた [santa]
- さんか [saŋka]
この3つの単語は、日本語母語話者だと同じ「ん」として認識する人が多いと思いますが、よく考えて発音すると、実は違う音です。
そう考えると、 /N/という音素は、複数の音を含めた抽象的な音の単位と考えられます。

↑図に表すとこんな感じです。
こういう抽象的な音の単位の構成をもとに、その言語の音声体系や構造を探るのが音韻論です。
また、[m] [n] [ŋ]などの、実際に使われている音がどうやったら発音できるのか、どう伝達されて知覚されるのかを対象にするのが音声学です。
音声学・音韻論の射程
音声学
音声学のほうは、「言語音の諸特徴を記述する」とありますが、人間が発するあらゆる音声を対象にします。
実際に使われている音を対象にし、その音がどう調音され、どう伝達され、どう知覚されるのかを研究する分野です。
参考にした本音声学とその分野について紹介したいと思います。 今回の記事を書くときに、以下の本を参考にしています。 川原繁人(2015)音とことばのふしぎな世界: メイド声から英語の達人まで. 岩波書店[…]
また、音声学では音声を記述するといいましたが、記述にあたっては、国際音声記号(IPA)という国際的な音声記号があります。
音声学の特徴として、ある言語に限ったことではないということがあります。人間が使う「音声」に着目しているので、ユニバーサルな傾向が強いです。
音韻論
音声学が実際に使用されている音声を対象にするのに対し、音韻論はある言語の抽象的な音声体系・構造を対象にします。
音韻論とは?音韻論(phonology)とは、「音の文法」に関する分野です。(斎藤他2015)「音に文法があるの?」と思うかもしれませんが、あります。例えば、「いぬ」と「ことば」を組み合わせて新しい複合語を作るとき、「い[…]
音韻論では、各言語に存在する「音の文法」を明らかにします。
音声学が言語間で普遍的な特徴を探る傾向があるのに対し、音韻論はそれぞれの個別の言語にどんな音声体系・構造があるか調べる傾向があるという特徴があります。
まとめ&ご興味のある方は
音声学と音韻論の違いについて簡単に説明しました。まとめると以下のようになります。
- 音声学:言語音の諸特徴を記述する。また、音がどう調音され、どう伝達され、どう知覚されるのかを研究する。
- 音韻論:意味の弁別に関与する最小単位である音素の特定やその分布の研究を行う(庵 2001, p. 4)。また、各言語に存在する「音の文法」を明らかにする。
ご興味のある方は以下の記事もご覧ください。