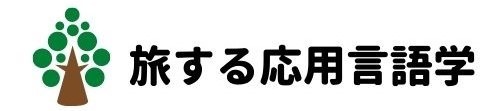言語計画の3つのアプローチについて
言語政策というのは、言語に対して何らかの意図や方針をもって介入する試み(木村 2015)のことをいいます。
特に、あるコミュニティでの言語環境を変えるための一連の計画のことを「言語計画(language planning)」といいます。
言語計画については、大きく分けて以下の3つのアプローチがあると言われています(Hornberger 2006)。
- 席次計画(Status planning)
- 実体計画(Corpus planning)
- 習得計画(Acquisition planning)
この記事ではこの3つのアプローチについて簡単に紹介します。
なお、このそれぞれの英語の日本語訳は、例えばstatus planningの場合は「席次計画」や「地位計画」があったりと、複数存在します。
この3つ以外にも、威信計画(prestige planning)といって、ある言語コミュニティの民族アイデンティティに関係する価値観を形成する計画も提唱されています(Haarman 1984)。
席次計画(Status Planning)
席次計画(status planning)は、ある社会における言語の地位に関連するアプローチです。地位計画と訳されることもあります。
席次計画には以下のような例があります。
- 公用語や国家語を定める。
- 学校教育の授業で使用する言語を定める。
例えば、マレーシアは多民族国家で、マレー人、中国人、インド人やそのほかの民族など多様な民族がいて、英語やマレー語やタミル語、マンダリン(北京語)、広東語、福建語など様々な言語が使用されています。
ただ、公用語はマレー語のみになっており、複数ある言語の中でマレー語の地位を特別なものとするという意図がみられます。
お隣のシンガポールも、マレーシアと同様に多民族国家です。シンガポールでは、国語はマレー語で、公用語として英語・中国語・マレー語・タミル語の4つが定められています。
このようにどの言語にどの地位を与えるかに関連するアプローチを席次計画といいます。
実体計画(Corpus planning)
実体計画は、実際に使われる言語の内容に対するアプローチです。本体計画やコーパス計画とも訳されます。
マレーシアでは、公用語がマレー語になっています。ただ、マレー語といっても多様な変種があり、話者によっても使い方が違います。
実体計画は、数あるマレー語の変種の中から、どのマレー語が学校教育や行政・司法等の公的な場で使うには適切なマレー語なのかといったことを決めるものです。
実体計画には以下のような例があります。
- 話し言葉の正書法や表記法を決める。
- 標準語を定める。
- 辞書を編纂するなどして使用語彙を決める。
- その言語の文法書を編纂する。
日本語でも、一般の社会生活において現代の国語を書き表すためのよりどころとして、送り仮名のつけ方のルールや、常用漢字の選定、現代仮名遣いなどが内閣告示として提示されています。
これらは特に個々人の表記を規制するものではなく、あくまでよりどころとはされていますが、実体計画の一環といえるでしょう。
習得計画(Acquisition Planning )
習得計画は、言語の使用者に対するアプローチです。普及計画ともいわれます。
具外的には、コミュニティ、教育分野・学校、メディア、職場などで、どう言語を習得させ、普及させていくかに関するものです。
習得計画には、以下のようなものが含まれます。
- その言語の学習教材を開発をする。
- その言語を学べる機関を設置する。
- 学校でその言語のクラスを導入する。
例えば、日本語に関しては、国際交流基金が、国内外での日本語教育の充実のために教材開発をしたり、各国・地域の政府や教育機関と連携して学習環境の整備に取り組んでいます。
英語におけるブリティッシュカウンシルや、ドイツ語におけるゲーテ・インスティトゥートの活動も、習得計画に関するものです。
まとめと参考文献
この記事では、言語計画の3つのアプローチについて簡単に紹介しました。まとめると以下のようになります。
- 言語計画とは、あるコミュニティでの言語環境を変えるための一連の計画のことを言い、席次計画、実体計画、習得計画の3つのアプローチに分けられることが多い。
- 席次計画は、公用語の制定など、言語の地位に関する計画である。
- 実体計画は、標準語を決めるなど、使用される言語の内容に関する計画である。
- 習得計画は、教材開発など、その言語の普及に関する計画である。
なお、それぞれの言語的介入が3つのいずれかに厳密に分けられるわけではありません。学校教育における言語の導入など、席次計画と習得計画の両方に関係するようなものもあります。
この記事を書くにあたって参考にしたのは以下の文献です。
Cooperは上記の3つ目のアプローチの習得計画を提唱した学者でもあります。