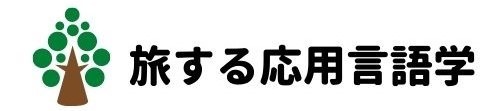語用論とは?
語用論は英語では「Pragmatics」のことです。「Pragmatic」とは「実用的な」「実利的な」「実践的な」という意味ですが、学問としての語用論(Pragmatics)はある社会文化的状況の中での言語の使用に着目した分野です。
具体的には、ある状況で話し手はどう自分の伝えたい意図を伝え、聞き手はどう意味を解釈するのか、そして両者がどう意味を構築しているのかを探ります。
これだけだとわかりづらいと思うので、以下の文を見てください。
- A: この部屋、暑いね…。
- B: クーラーつけようか?
Aが言ったのは、「この部屋、暑いね」というだけです。ですが、Bは、「そうだね、暑いね」と答えるのではなく、「クーラーつけようか?」と反応しています。
(実際にAが意図していたかどうかは別にして、)BはAの「この部屋、暑いね」という発話に、ただ事実を述べているだけでなく、「クーラーをつけてほしい」という別の意図を感じ取ったと考えられます。
もう一つの例を見てみます。
- A: 明日、飲みにいかない?
- B: すごくいきたいんだけど、最近ちょっと忙しくて…。
- A: そっか、残念。
この短い例でも、Bは「最近ちょっと忙しくて」しかいっておらず、直接「行けない」と言っていません。でも、Aは誘いを断ったと解釈しました。
Bの文字通りの意味(「最近忙しい」)を超えた意図をAが読み取ったと考えられます。
また、Bは、直接「行けない」と言わず、あえて「すごくいきたいんだけど」などの表現を使って相手に自分の意図を伝えようとしています。おそらく、Bの意図には「断りたいけど、相手の気分を害したくない」という配慮もあると考えられます。
このように、実際に言語を使用するときは、文字どおりの意味だけでなく、言外の意味(話し手の伝えたい意図や目的、前提など)が生じることがあります。こういった言外の意味はどう作られていくのか、そして話し手と聞き手はどう言外の意味を伝え、また解釈しているのかを探るのが語用論です。
言語学の音声論や音韻論、統語論、形態論などと違う点は「言語の実際の使用」に着目しているところです。
語用論研究
語用論について詳しく知りたい方には以下のような本があります。
語用論で扱う理論等をわかりやすく説明しています。
語用論の様々な研究法を紹介しています。語用論研究に興味がある人にはおすすめです。
語学を教えている方で、語用論の知見を言語のクラスで取り扱いたい人には、以下の本がおすすめです。
↑教室で語用論指導を主に記載した本です。なお、ずっと昔の記事でも書きましたが、この2人は実際に語用論を指導するためのウェブサイトも開発しています。
英語の入門書では、だいぶ古い本ですが、この本は日本の新書のように読めるので、短く読みやすいと思います。
他にも語用論の入門書などは複数出版されています。
その他の関連記事
言語学の諸分野に興味のある方は以下の記事もご覧ください。
- 言語学の諸分野について(音声学・音韻論・形態論・統語論・意味論・語用論)
- 言語学の意味論(semantics)とは何か?
- 形態論(morphology)とは何か?
- 統語論(Syntax)とは何か?
- 音声学とその3つの分野(調音音声学・音響音声学・知覚音声学)について
- 音声学(phonetics)と音韻論(phonology)の違いについて
- 応用言語学とは?
このサイトでも以前から語用論に関する書籍・論文などを紹介しているので、もしご興味がある方は他の記事もご覧ください。
- 理論的研究(言外の意味にはどういったものがあるのか、なぜ言外の意味が理解できるのか、相手の意図を読み取るプロセスや相手に意図を伝えるプロセスにルールがあるのかなど)
- 会話分析・談話分析
- 比較・ 対照語用論研究(言外の意味を表す際に言語間の違いがあるか(例えば日本語と英語の断り方などに違いがあるかなど))
- 中間言語語用論研究(学習者がどう語用論的要素を学ぶのか、どう指導するのか)