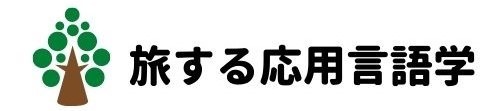万葉仮名とは
万葉仮名とは
万葉仮名は、漢字の持つ音を使って、日本語の音を表記する用法のことです。奈良時代によく見られた表記法で、ひらがな・カタカナが成立する以前に使われていました。
今は「カワ(river)」といえば「川」という漢字で書きますが、それを「加和」と漢字の音を使って書くようなものです。
漢字は一字一字が一定の意味を持つものです。例えば、「加」や「和」というのは「カ」や「ワ」という音で読みますが、「加える」や「和む」という意味があります。
万葉仮名というのは、漢字の持つ意味を無視して、漢字の音のみを使うことで、日本語を表記するものです。
いってしまえば、当て字のことです。
今も「アメリカ」を「亜米利加」、「アジア」を「亜細亜」、「フランス」を「仏蘭西」と書いたりしますね。
なお、万葉仮名というのは、奈良時代の万葉集でよく使われていたからという理由で、「万葉」という名がつけられています。ただ、万葉仮名自体は、万葉集のみならず、「日本書紀」「古事記」などでよく見られます。
万葉仮名の起源
万葉仮名がいつ生まれたかは定かではないそうですが、そもそもは、漢文の中に中国語以外の固有名詞を書き表すために使用していたようです。
日本でも、埼玉県の稲荷山古墳から出土した鉄剣の裏面に以下のような記載があります。
其児名加差披余其児名乎獲居臣世々為杖刀人首奉事来至今獲加多支鹵大王寺在斯鬼宮時吾左治天下令作此百練利刀記吾奉事根原也
(ちなみに、この鉄剣は埼玉県立さきたま史跡の博物館で見ることができます)
この赤字で示した「獲加多支鹵(ワカタケル)」というのは人名です。漢文の中で、このように固有名詞を、漢字の音のみを使って示していたのですね。
この鉄剣は471年のものだと言われていますので、この時代から漢字の音を使って、日本語の音を表記することは行われていたことが見て取れます。
平安時代までは、平仮名・片仮名はまだ存在していませんでした。
なので、固有名詞のみならず、日本語のことばを表記したいときに、万葉仮名を使用して表記するようになりました。
万葉仮名は、万葉集の中に豊富にみられますが、万葉集は「歌」ですから、音の響きが大切だったと考えられます。
漢文に翻訳してしまったら雰囲気が伝わらなくなってしまうので、日本語の音を記したかったのかもしれません。
なお、万葉集で使われる万葉仮名は「恋」を「孤悲(こひ)」と書くなど、漢字の意味を少しいかしたようなものもみられるようです(森山・渋谷 2020 p. 33)。人間の工夫がみられて面白いですね。
万葉仮名の例
万葉仮名の例としては以下のものがあります。
スサノオノミコトが詠んだとされる和歌です。
夜久毛多都 伊豆毛夜幣賀岐 都麻碁微爾 夜幣賀岐都久流 曾能夜幣賀岐袁(古事記全文検索より抜粋)
ここの読み下し文は、「八雲立つ 出雲八重垣 妻ごみに 八重垣つくる その八重垣を」です。
- 夜久毛多都 → 八雲立つ
- 伊豆毛夜幣賀岐 → 出雲八重垣
- 都麻碁微爾 → 妻ごみに
- 夜幣賀岐都久流 → 八重垣つくる
- 曾能夜幣賀岐袁 → その八重垣を
となっているのがわかりますね!
なお、万葉仮名は一つの音を表すのに、複数の表記がありました。
例えば、「あ」を表す音は、「阿」「安」「吾」「足」など複数ありました。これが後々、当時の日本語の発音を示唆する資料としても使われるようになっていきます。
ハ行転呼音とは?ハ行転呼音とはハ行転呼音とは、語中・語末のハ行の子音が、ワ行音になったことを言います。そもそも、「転呼音」というのは、語中・語尾の音を、その語の書き表す仮名の発音ではなく、別の音に発音することをいいます。[…]
万葉仮名には、漢字の音読みの音を用いた「音仮名」と、漢字の訓読みの音を用いた「訓仮名」があります(森山・渋谷 2020 p. 33より引用)。
- 音仮名の例:波奈(はな)・安吉(あき)・南(なむ)・甲斐(かひ)
- 訓仮名の例:為酢寸(すずき)、夏樫(なつかし)、五十(い)
万葉仮名の影響・平仮名と片仮名
平仮名も片仮名も、平安時代に万葉仮名をもとに作られました。
万葉仮名は画数も多いので、いちいち書くのは不便でした。なので、くずしたり、省略したりすることで平仮名・片仮名が生まれます。
平仮名は、万葉仮名の草書体をさらにくずして作ったものです。

(wikipediaより引用)
片仮名は、以下のように、万葉仮名の一部を使って作られました。

(wikipediaより引用)
まとめ
万葉仮名について簡単に紹介しました。まとめると、以下のようになります。
- 万葉仮名とは、漢字の持つ音を使って、日本語の音を表記する用法
- 万葉仮名を基に、平仮名・片仮名が生まれた。
何かのお役に立てれば幸いです。
日本語の文字に興味のある方は、以下のような本があります。